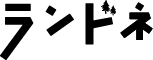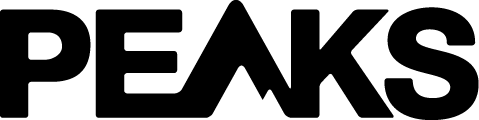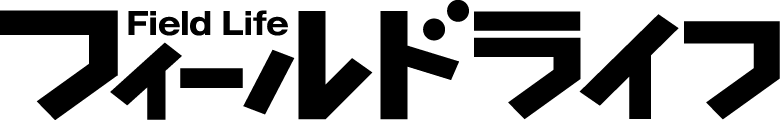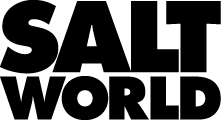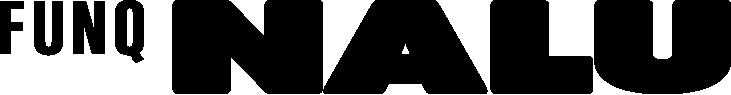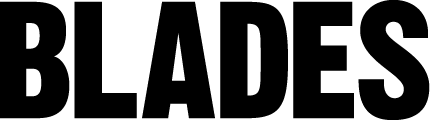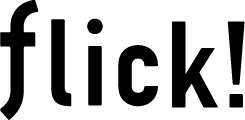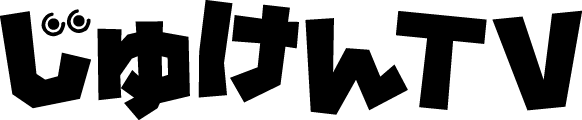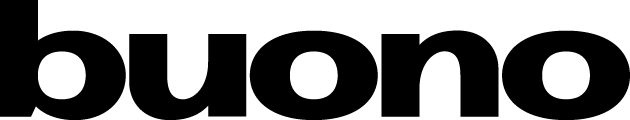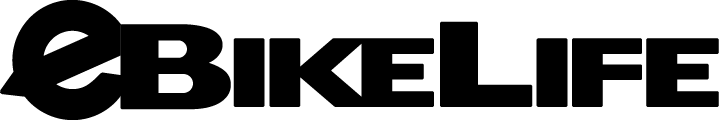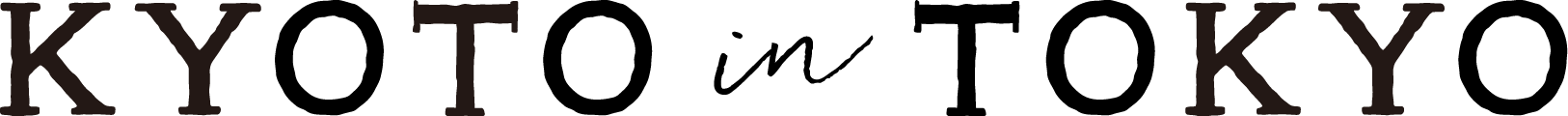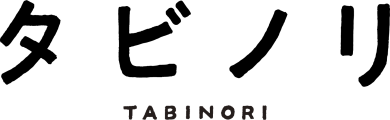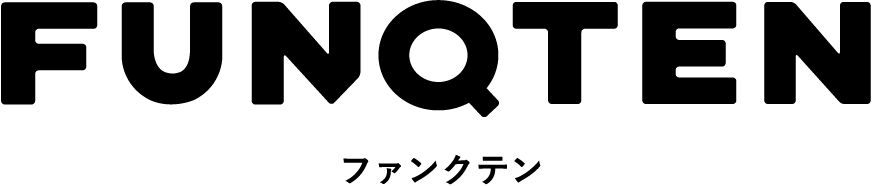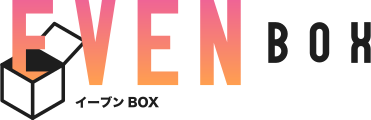「キャー、コマクサきれいね♡」…それ、クワセモノの女王かも!?│|植物ライター・成清 陽のヤマノハナ手帖 #49
成清 陽
- 2025年10月05日
INDEX
登山&撮影をライフワークとする花ライターがお送りする、高山植物の偏愛記。静かに、しかしアツ~く、お花をご紹介します!
前回、燕岳取材にてお送りしてきたコマクサの大群落。今も思い返せばヨダレが出るほど、サイコーの風景でした。そして聞けば、なんと大雪山などでも、自生コマクサが見られるのだそう。しかしいっぽうで、同じ北海道の樽前山や羊蹄山では、妖艶な女王・コマクサに惑わされた人々が引き起こす、大問題があるのだとか。今回は、コマクサという「国内外来種」について対策をとっている、ふたつの拠点を取材。その実態を、教えていただきました!(上写真提供:支笏洞爺国立公園管理事務所)
“善意”ってそれ、“軽いキモチ”でしょ!
昨年、高山植物の殿堂・大町山岳博物館でのコマクサ取材中に話題にあがったのが、北海道へのコマクサ“移入”問題。いや、高山植物の女王に向かって移入とは無礼な!と思いつつも、まずは樽前山が位置する支笏洞爺国立公園の管理運営を担う、同国立公園管理事務所を取材しました。
取材に答えてくださったのは、国立公園管理官の荒川真吾さん、そしてアクティブレンジャー(自然保護官補佐)の奥脇百花さん。衝撃の事実を語ってくれました。「樽前山に持ち込まれたのは、1970年前後、2000年代など、複数回持ち込まれている可能性があるんです。今ほど生物多様性や自然環境保全の概念が浸透していない時代、推測ですが『ここでコマクサが見られたらいいな』という軽い気持ちで植栽したと思われます」。ななな、なんという不届き者~!!と思わず斬りかかりそうに(?)なりましたが、ふと我にかえると素朴な疑問がプカリ。コマクサって、やっぱり植栽しちゃダメ……なんですよね?

やり場のないキモチ、どうすればいいんじゃ~
「過去の文献からも、もともとここにないことは明確ですし、国立公園内では原生の自然や在来種が大切です。特に樽前山では、科学的なデータこそありませんが、イワブクロ(タルマイソウ)などの在来植物の生育を、脅かす可能性があると考えられているんです」。ほほう、では成敗すればいいのはコマクサか!いざ……。「いえ、そうではなくて汗。コマクサ自体には、罪はありません!しかし、放置もできません。そのため、5月末と6月の年二回、パークボランティアと連携し、樽前山コマクサ除去活動を行なっています」。
悶々……です。だっておふたりは、自然が好きだからこそ、入省したんですよね?「そうです。そのため、このコマクサが自然分布だったら、といった気持ちもあります。樽前山には、溶岩ドームの特異な景観や生態系があります。コマクサの移入問題を通じて、コメバツガザクラやイワブクロといった在来種がイキイキ過ごせる本来の生態系や環境とはどういうものなのか、登山道を外れないといったマナーにも関心を持っていただけたら」。
当事者おふたりの気持ちを考えたら、涙が出そうでした!

Data
樽前山の移入コマクサ(写真中央は、在来種のイワブクロ;コマクサの小さな株は、右下に!)
持ち込み年代と記録:1986年、苫小牧民報に掲載
生育地の数:10カ所程度
2025年度除去実績:株数約3,426本(2330.5g)
実施日:5月29日、6月10日/27名動員
百名山・羊蹄山にもコマクサが
さて、ところかわって蝦夷富士の名で知られる羊蹄山。こちらでもコマクサの持ち込みがあり、樽前山同様に除去が行なわれてきたのだとか。その実態については、2017年からこの活動に参加してきた、倶知安風土館の小田桐亮さんに伺いました。
「羊蹄山のコマクサが発見されたのは、1998年です。

女王ご引退に向けて、人々が団結
本州コマクサの種をまいたためか、意外や野生っぽい気品もある、こちら。でも、やっぱりここにあってはならないものなんですよね。「本来そこにいなかったものを放っておくと、昔からいたと扱われかねません。これは、山の成り立ちを歪めてしまう可能性があるんですよ。
こちらでは「コマクサ駆除事業」と銘打って始まった、除去作業。発見の翌年、1999年7月にスタートしたそうです。「倶知安町教育委員会が主となって始まったこちらは、洞爺湖管理官事務所が実施、その後は私の所属する倶知安風土館と、ニセコネイチャーガイドネット(NNN)所属のガイドさんをメインとして、進めてきました。地域課題であるコマクサが発端となり、ガイドさんたちの横のつながりができたそうですよ」。高山植物女王への強い不信感が、民衆を動かした、みたいな?なんという皮肉……。

Data
羊蹄山の移入コマクサ
持ち込み年代と記録:1998年、北海道新聞に掲載
生育地の数:ほぼなし(継続的な除去活動による)
2025年度除去実績:0株
女王様、ひと皮むいたら雑草でした
樽前山に比べ除去活動が進んだ、羊蹄山。現在、コマクサ駆除は年に1回、1日行なわれるのみですが、花をつけた個体(有花茎)は、ほぼ見当たらなくなりました。しかし、そこに至るまでにも、ドラマチックな展開アリ!
「羊蹄山は、斜面での分布面積が少ないのが、樽前山との違いでしょうね。ただ、羊蹄山は登山行程が長いですから、体力と覚悟が必要です。そして、当初は充実した有花茎個体が、半径70~80cmにもわたって根を張っていたと聞きます。当時は抜き取りのノウハウが蓄積されていなかったため、地上部だけを取ったら、地中に残ったコマクサの根が再生し、ひとつの株が4つに分かれる例もあったというんです!地上部の可憐さとは裏腹ですよね~」。こりゃ~もはや、雑草魂。女王じゃなくて、地下アイドルっぽい……。

駆除の目的、ご理解ヨロシク!
そしてね、難しいのはやっぱり世論。ニンゲンってとっても勝手なもので、コマクサ駆除の件が新聞に載ると、かつては批判もあったそうです。「コマクサはやっぱり、特別視される存在。でも、コマクサがいることで、在来の植物が死んでいっている背景もあるんです。かわいそうといった感情とはしっかり切り分けて、『もとあった姿に戻す』という目的を、明確にしなくてはいけません。これからもコマクサ抜き取りの熟練者はもちろん、登山者の皆さんのお力添えで、もとの羊蹄山に戻していきたいです!」。
成果は上がりつつも、まだ終わりが見えない、羊蹄山のコマクサ除去。片道5時間ほどかかる登山を経てまで、駆除に携わる方々の苦労もしのばれます。そしてやはり、「美しいからみんなに見せたい」などという安直な発想は、ご法度。“豊かな自然”は確かに美しい花がつきもの。でも、“持ち込みはダメゼッタイ!”これ、ハイカーの皆さん全員の常識にしていきましょう~!!

さてさて、今回ご紹介してきた、北海道へのコマクサ移入問題。いかがでしたでしょうか?取材を進めるうち、コマクサの雑草的な生態までも見えてきちゃいました。そして、ニンゲンという生き物の、誘惑に弱い側面も……。編集部Yさんからいただいた、「女王蟻、女王蜂、コマクサなど、植物や昆虫の世界での女王とは、『繁殖』を示すんですね!」というコメントにも、うなずくばかりでした。そんな優秀な編集部に、一点だけ提言。「コレは現地に行かねば!!来年は自家用ヘリ飛ばして、取材に行きましょっ♪」。
※たとえ国内外来種とはいえ、国立公園の特別保護地区&特別地域内、国有林内などでは、植物の勝手な採集は禁止されています。あしからずご了承ください
それでは、また。
皆様のココロに、素敵な花が咲き誇りますように。
SHARE