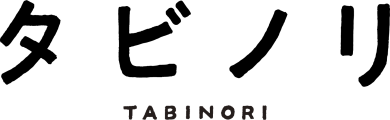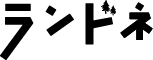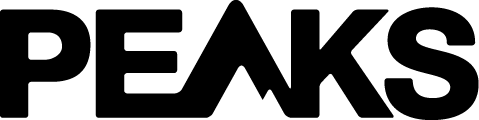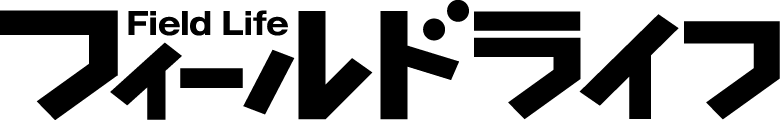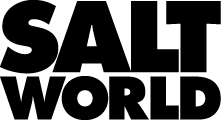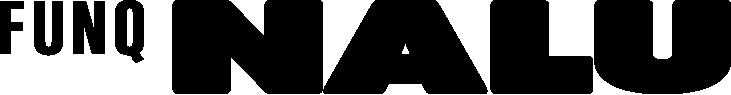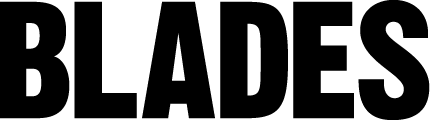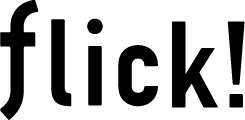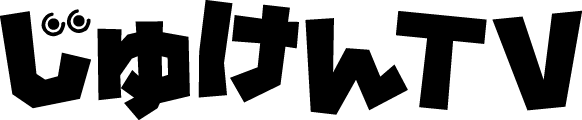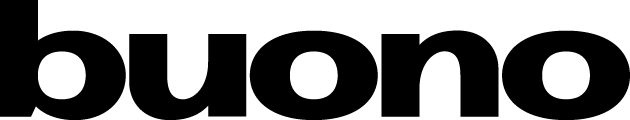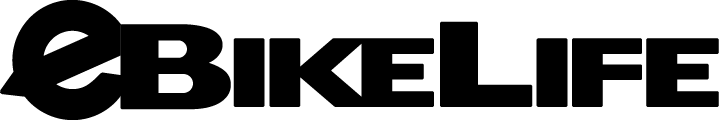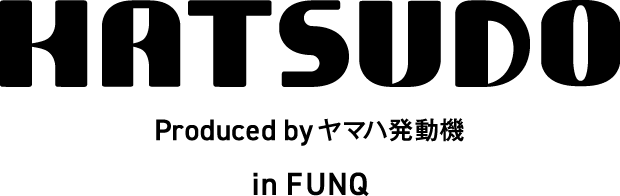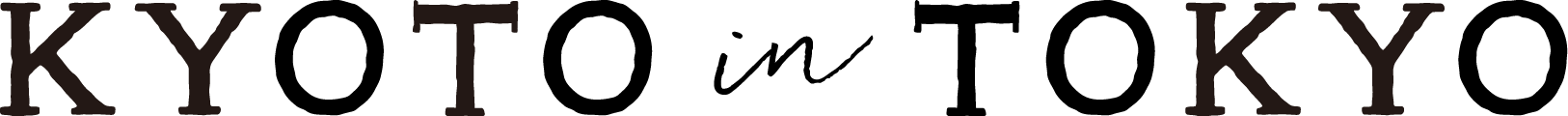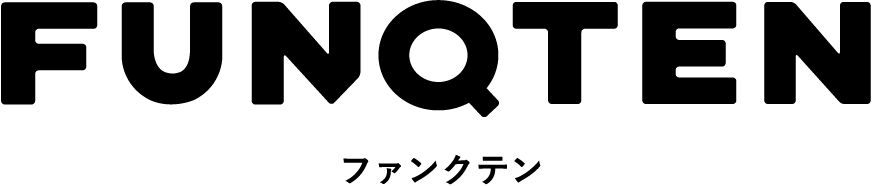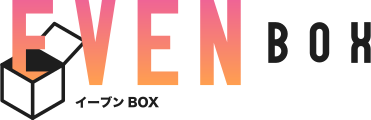航空機ファンだけじゃない!クルマ好きも電車好きも「あいち航空ミュージアム」へ訪れるべき理由 [名古屋特集]
タビノリSTAFF
- 2025年10月17日
クルマや電車など、乗り物をテーマにした博物館に足を運んだことはあっても、航空機の博物館となるといかがだろう。日本国内には航空機の実機を展示した博物館が約10か所ほど運営されているが、中でも「あいち航空ミュージアム」は、航空ファンだけでなく、クルマ好き、鉄道好きなら、一度は訪れるべき施設といえるかもしれない。
ゼロ戦が生まれそだった愛知は日本の航空宇宙産業の集積地
第二次世界大戦の開戦当初、長い航続距離と優れた運動性能で、連合国の名だたる戦闘機を凌駕する性能を誇った旧日本海軍の主力戦闘機「零式艦上戦闘機」、通称「零(ゼロ)戦」。その開発は、三菱重工業で設計主任だった堀越二郎技師により設計、名古屋市の同社大江工場で製造された。いわば名古屋は零戦の生まれ故郷といえる地域であり、実は現代においても、愛知を中心とした中部地区は全国の航空機部品生産額等の5割以上を占める航空宇宙産業の集積地だ。
東海道新幹線「名古屋」駅から、タクシーまたは、「あおい交通」の空港直行バスで約20分ほどにある「県営名古屋空港」。愛知万博の開催に合わせて「中部国際空港 セントレア」が開港する以前までは、国際線も受け入れていた名古屋空港は、現在国内線を中心としたリージョナル(地域)空港として、客席数が50~100席の小型ジェット機利用されるローカル空港となっている。

かつての国際線ターミナルビルは現在、「エアポートウォーク名古屋」として空港隣接のショッピングモールとして活用されており、出国カウンターを利用したフードコートや、駐機場の跡地を転用した駐車場など、施設の随所に当時の面影を見ることができる。
これだけでもユニークなのだが、そんなエアポートウォーク名古屋の館内を進み、2階に上がり元ボーディングブリッジだった渡り廊下を進むと、県営名古屋空港の敷地内にある「あいち航空ミュージアム」にたどり着く。
名古屋空港内に立地する地の利を生かした「あいち航空ミュージアム」だけの体験


あいち航空ミュージアムは、2017年11月に愛知県営名古屋空港内に開館した、航空機の歴史や仕組みを学べるミュージアム。国産初のプロペラ旅客機「YS-11」など、県内で開発された航空機の展示をメインに、すべてハンドメイド(!?)による日本の航空機の歴史に名を残した模型を展示したスペース「名機百選」や愛知県の航空機産業の歴史などが学べるオリエンテーションシアターにフライトシミュレーター、ミュージアムショップやカフェといったスペースを設置。一部は機体内部に搭乗することもできるなど、大人から子供連れまで時間を忘れて楽しめる、愛知県が航空分野の産業観光拠点と位置付ける施設だ。


展示で目を引くのはやはり巨大な格納庫状の館内に展示された実機の展示ゾーンで、中でも零戦は外せないだろう。この機体、実は映画「永遠の0」でも使用された実物大模型なのだが、開館当初は、かつての三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所史料室(豊山町)に展示されていた実機を借り受け展示していた実績も。模型とはいえ、現物を目の当たりにすると、戦争の痛ましい歴史と、この地が生まれ故郷であった現実をリアルに感じとることができる。

近年、なにかと話題の「ブルーインパルス」が使用する「T-4」、戦後初の国産航空機「YS-11」など、普段搭乗する航空機では決して味わうことができない、手を伸ばせば触れられるような目前で見る実機の迫力は、航空ミュージアムならではの体験だろう。

しかも、屋上の展望デッキに上がれば、このミュージアムが他の航空ミュージアムとの決定的な違いを体験できる。目前にある県営名古屋空港を離発着するカラフルな民間機の姿に加え、救急のドクターヘリ、奥にある航空自衛隊小牧基地に駐機する自衛隊機や、三菱重工業の工場で整備を受ける最新鋭のF-35の機体まで運がよければ拝めることも。


これらは、本施設が空港内にあるミュージアムなればこそ。展示された動かない歴史的な国産の実機と、轟音と共に飛行する最新鋭の実機の両方を拝めるミュージアムというわけだ。
なぜ、愛知・名古屋に航空機産業が盛えたのか
そもそも、なぜ愛知では戦前から航空機産業が栄えていたのか。取材当日、現地を案内していただいた施設の指定管理会社「名古屋空港ビルディング」ミュージアム運営部の金武倫明氏に聞いてみた。
「元々航空機を飛ばすのに適した広い土地があったということもありますが、名古屋を中心とした周辺地域には、戦争が終結するまで、国内を代表する4社(三菱・愛知航空機・中島飛行機・川崎航空機)の航空機工場が軒を連ねていました。現在でこそ愛知といえばクルマというイメージですが、かつてこの一帯は国産航空機の一大生産拠点だった歴史があるのです。
元々、黎明期の航空機は木材を材料としており、愛知県は木材加工の技術力に優れ、近隣には良質な木材の生産地があったこと、また、東京と大阪、東西物流のほぼ真ん中に位置し、貨物で運ぶにしても適した土地であったことも発展に寄与した理由でしょう。
ところが、終戦後、アメリカのGHQにより、国内の航空機は製造・運用や研究、教育までもが禁止されました。これにより、日本の航空機産業はプロペラ機からジェット機へ移行する際に、大きく乗り遅れてしまうことになりました。一方で、この地域には、当時零戦を筆頭に、航空機に関する最先端の知見を持ったあらゆる技術者が集っていたわけで、彼らは航空機以外に活躍の場を求めて方々に散っていきました。それが、後の自動車であり鉄道だったわけです。
立川飛行機で戦闘機『キ94』の設計を担った長谷川龍雄氏は戦後トヨタに入社し、『パブリカ』や『カローラ』といった大衆車の開発主任となり、特攻機『桜花』の開発に携わった三木忠直氏は、戦後その反省から軍需利用の可能性が低い国鉄の車両技術者へと転身し、初代新幹線『0系』の先端のデザインを設計したことで知られます。零戦の墜落事故調査で活躍した松平精氏は、鉄道の揺れと零戦の不安定な翼の振動検査をヒントに、鉄道の脱線事故の原因を解明し、後にこの技術を生かした技術が新幹線へと受け継がれることになりました。
零戦のエンジンを製造していた中島飛行機、現在の『SUBARU』が採用している水平対向エンジンは、元々は航空機のために、水平対向のレイアウトとすることで振動が打ち消しやすいという発想から生まれたものですし、日産自動車の前身ともいえる、『スカイライン』を生んだ『プリンス』社も当初は立川飛行機の元技術者なのです。
日本の技術者の源流が、戦時下からこの地にあり、現在にも受け継がれているという土壌があるのです。航空機の形状は空力に対するデザインの集約であり、振動が少ない高出力なエンジンは後の自動車産業に大きく寄与したわけです。
実は、先ほどあげた4社の飛行機メーカーの内、愛知航空機を除いては、戦後、航空機一機まるごとは作らないまでも、分業の中では航空機産業に参入を続けており、例えば『ボーイング787』の翼の一部などは、国内で部品を製造し、アメリカへ輸出しています。

川崎重工は中等練習機『T4』、哨戒機『P-1』など自衛隊の航空機を製造し、三菱重工は戦闘機、『F-1』、『F-2』を開発し、自衛隊に配備されている最新鋭の『F-35』はアジアでは唯一、この施設からも見える、三菱重工業小牧南工場でのみメンテナンスが可能です。
実は、本ミュージアムが県営名古屋空港に隣接した形で計画されたこと自体、国産初の小型ジェット旅客機として三菱重工業が政府と一体となって開発を進めたものの開発が中止となった『Mitsubishi Regional Jet(三菱リージョナルジェット※以下MRJ、後にMSJ)』の開発拠点こそ、この小牧南工場であり、開発が成功していれば、同工場で生産されたMRJがこの空港からどんどん世界に飛び立っていく様子が見られたのです。残念ながらその可能性はなくなってしまったのですが。
ただし、本ミュージアムは他の航空ミュージアムには決定的な違いがあります。それは、空港の中にあるという立地です。毎年秋には名古屋空港が防災拠点であることをいかした消防航空隊の実機や、隣接する航空自衛隊小牧基地の戦術輸送機・救難ヘリなどの実機、警察航空隊の警察ヘリコプターなどの実機を普段は立ち入ることのできないエプロン(駐機場所)内に入り、実機見学や隊員の話を聞くといったイベントを開催しています。
これは、空港内にある本ミュージアムだからこそ可能なイベントといえるかもしれません」

世界をリードした航空機産業のDNAが受け継がれた事実を体感
あいち航空ミュージアムは、単なる実機の展示に留まらない奥深さがある。
国産航空産業の発展を実機を通して体感できる一方、戦争という悲しい目的の下に世界最先端級の航空機技術を短い期間で磨き上げながら、戦後活躍の場を奪われたエリートエンジニアたちが、ある者はそのまま航空機に、ある者は自動車へ、ある者は鉄道へと、新天地でそれぞれの力を発揮していったプライドと想い、国産ジェット旅客機の夢まで、見る者に様々な感情を与えてくれる、そんな上質な大人の社会科見学であるといえるだろう。
infromation
SHARE
PROFILE

タビノリSTAFF
『タビノリ』は、旅の楽しさは、旅のはじまりである「移動」から、旅前の準備、ふとした寄り道、車窓から見つけるお気に入りの風景など、旅の余白に目を向け発信していくメディアです。また、旅をその周縁のものと組み合わせ、定番の旅先や新しい旅の提案などを仕掛けていきます。
『タビノリ』は、旅の楽しさは、旅のはじまりである「移動」から、旅前の準備、ふとした寄り道、車窓から見つけるお気に入りの風景など、旅の余白に目を向け発信していくメディアです。また、旅をその周縁のものと組み合わせ、定番の旅先や新しい旅の提案などを仕掛けていきます。