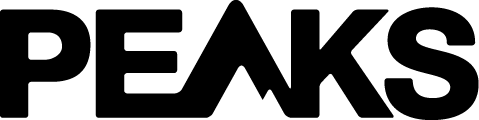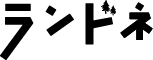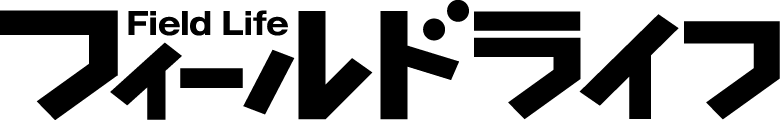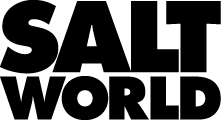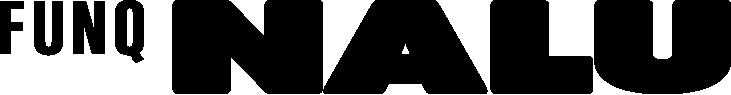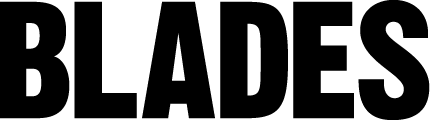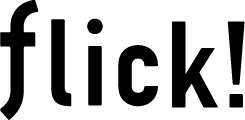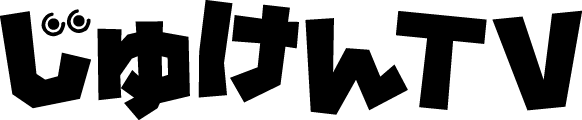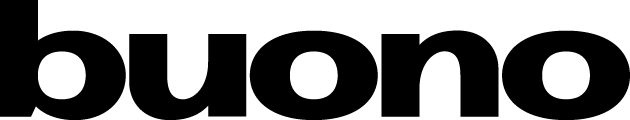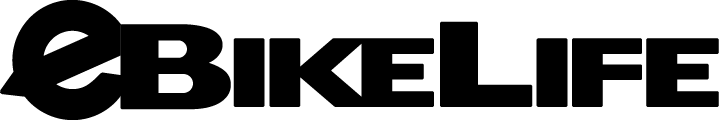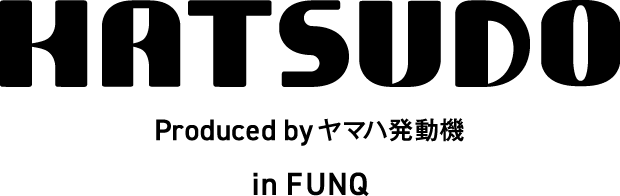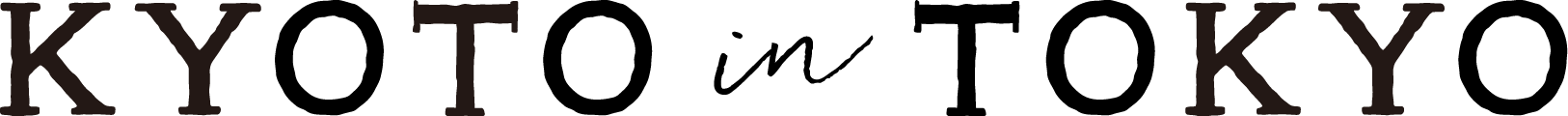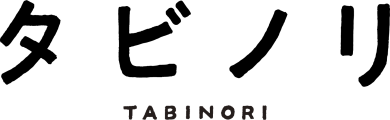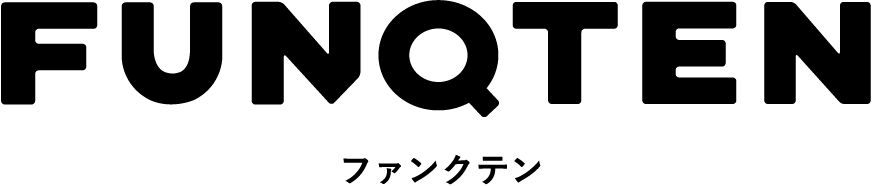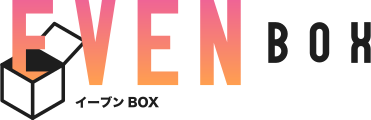連続登山で気づいたこと|100 MOUNTAINS, 100 STORIES. -日本百名山、映像と巡る150日‐vol.5
TAKE
- 2025年09月09日
INDEX
「日本百名山全踏破」に挑戦中のTAKEさん。
スピードアタックではなく、映像撮影をしながら、日本の登山文化や山の魅力をたくさんの人に伝えることが目的の旅だ。
5カ月間(150日)をかけて歩く“旅の裏側”の記録、第5回。全100座の約1/3を登り切ろうといういま、旅を通して気づいたこととは?
文・写真◉TAKE
編集◉PEAKS
\ vol.4はこちら /
連続で登山して感じたこと
7月に入り、日光・尾瀬エリアの赤城山、燧ヶ岳、至仏山を歩き、さらに上信越の苗場山・巻機山・越後駒ヶ岳へと北上を続けた。ここまでで、越後駒ヶ岳を含め31座。旅は39日目を迎えていた(うち15日は停滞日)。これほど連続して山を歩き続けると、普段は意識しないような自然の「共通性」や「土地ごとのリズム」に気づくようになる。
たとえば尾瀬や上越の山々。同じエリアの山は、やはり似ている。残雪を抱えた稜線や、雪解けの水が育む湿地ではワタスゲやニッコウキスゲが群れ咲き、山頂ではトンボが雲のように飛び交う。火山の隆起によって形づくられた山容はなだらかで大きく、歩いていると「ああ、このあたりの山はこういう表情なんだな」と自然に感じられる。日光の男体山や日光白根山、皇海山に目を向ければ、そこではまた鹿の多さや噴火の痕跡が残る荒々しい山肌に共通点がある。エリアごとに固有の特徴があって、それが何座も歩くうちに浮かび上がってくる。
山を単体で登っているときにはなかなか見えてこないことも、同じ季節に連続してエリアを渡り歩いてみると、「似ているな」「ここもそうか」という小さな気づきが積み重なっていく。その積み重ねはやがて学びに変わり、さらに次の山への興味を呼び起こす。だったら越後三山はどうだろう。八海山や中ノ岳はどんな姿をしているのか。そんな問いが次々と浮かび、自然と歩みを進めたくなる。
山を一座ごとに攻略していくのも楽しいけれど、エリアを定めてその土地の山々を同時期に歩いてみる。そうすることで、その地域ならではの気候や植生、山容の特徴をまるごと体感できるおもしろさがあるのだと、この旅で実感した。


日帰り難関、平ヶ岳
7月11日。日本百名山のなかでも「日帰り難関」と名高い平ヶ岳に挑んだ。登山口は国道352号沿いの鷹ノ巣登山口。往復20km、コースタイムは11時間。長大な行程に気持ちを引き締め、午前5時に歩き出した。
序盤こそ林道歩きだが、尾根に取りつくといきなり息を呑むような急登が始まった。下台倉山、台倉山と通過するたび、またも尾根、またも登り。まるで試されるかのように登坂が続き、天気も微妙で青空は見えない。まだ山頂の姿さえつかめず、果てしなさに気持ちが揺さぶられる。
やがて陽光が差し込むと、体力は容赦なく削られていった。国道352号にはコンビニすらなく、加えて越後駒ヶ岳での停滞で朝食も十分に取れていなかった。こまめに行動食を口に運んでも追いつかず、気づけば全身がバテバテ。そんな自分を叱咤しながら、一歩一歩、池ノ岳を目指す。
そして──池ノ岳にたどり着いた瞬間、景色が一変した。そこには池塘とワタスゲが広がり、霧を押しのけるように青空が広がったのだ。さっきまでの苦しさが嘘のように吹き飛び、心が震える。ここから山頂まではわずか30分。まるで夢の楽園を歩くように、アルプスとも違う、広大でどこか北海道を思わせる山容が目前に広がっていた。たまご石までの木道も、空の青とワタスゲの白に彩られ、足取りは軽くなる。
小屋もなく、水場も限られる。そんな厳しい条件が平ヶ岳を「日帰り難関」にしているのだろう。しかし、だからこそ到達した先の景色には重みがある。
長い登りを越えてたどり着いた先に広がっていたのは、言葉を失うほどの景色だった。だだっ広い稜線と空の青さに圧倒され、ただ立ち尽くすしかなかった。きつい道のりを歩いてきたからこそ、この光景の価値がいっそう大きく感じられる。最難関と呼ばれる山だけれど、その名に違わぬ特別な一座だった。
下山後は道の駅尾瀬檜枝岐で名物のそばをすすり、駒の湯で汗を流した。疲労のなかに満ち足りた充足感を抱え、翌日に向かう会津駒ヶ岳の登山口・滝沢へと車を走らせた。

心身の成長
平ヶ岳を終え、32座目。ついに全体の約1/3を歩き切った。振り返ると、明らかに身体が変わってきたのを実感する。以前なら1日7~8時間の登山は大仕事だったが、今ではほとんど苦に感じない。それどころか物足りなささえ覚えることがある。
体力だけではない。精神面にも変化があった。最初のころは「何時に山頂へ着けるか」「撮影時間が足りるか」と焦りが先行し、風景をじっくり楽しむ余裕がなかった。だがいまは、そうした焦りが薄れ、落ち着いた気持ちで山を歩けるようになっている。おかげで山頂に至るまでの道のりも、植生の変化や山容の違い、目の前に広がる展望を味わいながら撮影に集中できるようになった。
そして気づいたのは、登山に必要なのは「体力」だけではないということだ。毎日のように山を歩いていれば、疲労は確実に蓄積する。筋肉をほぐすマッサージやストレッチ、食事や睡眠で体調を整えることがケガの予防につながり、結果的に登山を長く楽しむための力になる。余裕ができたからこそわかったが、こうした“体をいたわる習慣”は登山のスキルと同じくらい重要だと感じる。
この心と体の余裕は、この旅における大きな成長だと思う。そしてこれは特別な旅だけに限らない。普段の登山でも、もし同じように余裕とケアを意識できたら、もっと安全に、もっと自然を楽しめるはずだ。だからこそ登山を快適に続けていくためには、定期的な運動に加えて、日々の体のメンテナンスを習慣にしていくことが大切なのだと強く感じた。

登山旅と映像制作
あらためて伝えておきたい。この旅の目的は日本百名山を制覇することそのものではない。すべてを映像として記録し発信することで、山や自然をより身近に感じてもらうことこそが真の目的だ。そのために重たい機材を担いで歩くのも想定内。しかし実際には「撮影すること」そのものよりも、準備や管理にかかる手間のほうが大きい。
撮影には、エリアの選定や必要な申請、機材準備、撮影本番、データ管理、編集、投稿と多くの工程がある。登山を続けながらこれらすべてをこなすのは現実的に難しいため、手続きやダイジェスト映像の編集などはサポートメンバーに協力してもらっている。それでも機材の充電やデータ整理、ショート動画の編集は自分の担当で、登山後の限られた時間にこなすことになる。
効率を少しでも高めるために、下山後すぐ機材の充電とデータ取り込みを開始するのが日課だ。とはいえバッテリー容量に限りがあるため、車での移動中に走行充電を活用している。大量のデータはSSDに保存し、定期的に郵送してサポートメンバーとやり取りしている。当初はクラウドやNASを使う計画だったが、山岳地での通信環境では現実的ではなかったからだ。
編集作業は停滞日にまとめて行なうが、カフェなどWi-Fi環境の整った場所を選ぶようにしている。結果として「山旅」と同時に「カフェ旅」も並行しているのが実情だ。効率よく作業できる環境を見つけるのも、この挑戦の一部になっている。
つくづく思うのは、山を歩くこと自体はとてもシンプルだということ。だが忘れ物をしないように準備したり、無理のない計画を立てたりすることが登山の成否を分けるように、この挑戦を広め、人に興味をもってもらうためには、“停滞日の行動”が結果を大きく左右すると思う。段取り八分、仕事二分。その言葉を実感する毎日だ。
思えば、この旅を始める前には、ソファに横たわり、ただスマホをスクロールするだけの、途方に暮れた時期があった。そこから抜け出すために立ち上げたのがこのプロジェクトだ。だからこそ成功の鍵は、山を歩き切ることだけではない。裏側の活動をどこまで頑張れるか。登山の疲れを言い訳にせず、自分を律し続けられるかにかかっていると信じている。
この挑戦の裏にある撮影機材や充電システムの工夫については、次回の記事で詳しく紹介していきたい。

『100 MOUNTAINS, 100 STORIES.』公式サイト
**********
▼PEAKS最新号のご購入はAmazonをチェック
SHARE